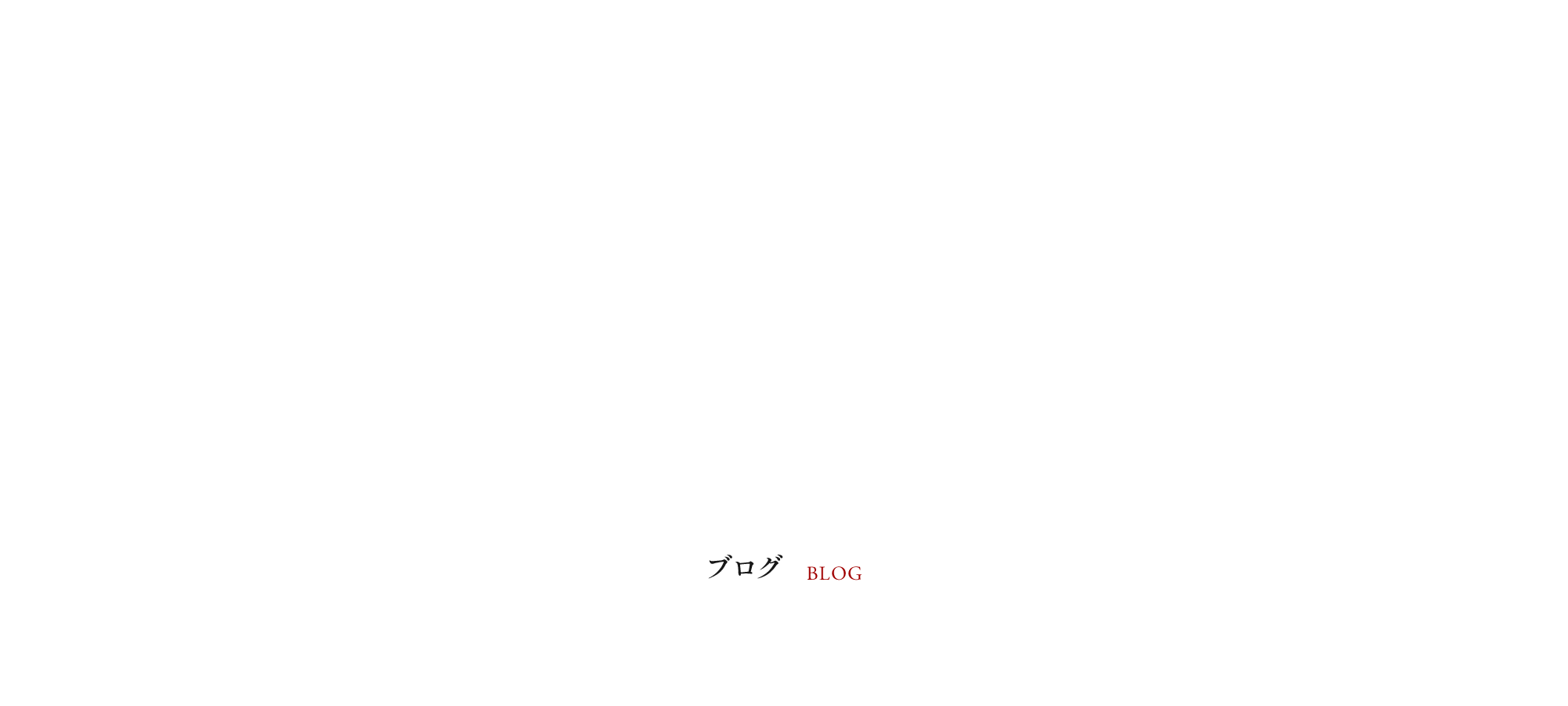
月別アーカイブ: 2025年11月
小浜あぐりの米米日記~一粒のコメからはじまる物語🍚~
皆さんこんにちは!
小浜あぐり合同会社、更新担当の中西です。
~一粒のコメからはじまる物語🍚~
先ほどは麦のお話をしましたが、
今回は日本の食卓になくてはならない**「お米」**について、
米農家の立場からお話ししてみたいと思います。
-
「お米って、どのくらい手間がかかっているの?」
-
「田んぼって、お米を作るだけの場所なの?」
そんな疑問を持っている方に、
米づくりの一年の流れや、田んぼが持っているたくさんの役割をお届けします🌱
1. 米づくりは“冬の準備”から静かにスタート❄️
田んぼと聞くと、青々とした夏の稲穂や、黄金色に染まる収穫期をイメージする方が多いと思います。
でも実は、米づくりのスタートはもっとずっと早く、冬のうちから始まっているんです。
冬の田んぼでは、
-
収穫後に残ったわらや株をすき込んで土に返す
-
土を寝かせながら、排水や水路の状態を整える
-
春の代かき・田植えに向けて機械のメンテナンスをする
といった作業が行われています。
雪が積もる地域では、
「今年は水が多めになりそうだな」「雪解けが早そうだな」
と、翌年の水管理のことも頭に入れながら過ごします☃️
米づくりにとって、“水”は命。
どのタイミングで、どのくらい水が入ってくるかをイメージしながら冬を過ごすのも、
米農家の大事な仕事なんです💧
2. 春、苗づくりから始まる“いのちのリレー”🌱
春が近づくと、いよいよ苗づくりが始まります。
ここからは、少しだけ時系列でご紹介します⏰
① 種もみの選別と温湯消毒
まずは、お米の“タネ”である種もみを選びます。
よく実の入った種を選び、
-
温湯(おんとう)で消毒して病気予防
-
水に浸して発芽の準備
を行います。
この段階での管理が甘いと、
発芽が揃わなかったり、病気のリスクが高くなったりするので、
地味ですがとても大切な工程です✨
② 育苗(いくびょう)トレーにまいて、ハウスへ🚜
その後、
育苗箱(苗箱)に土と種もみを均一にまき、
ビニールハウスや育苗ハウスの中でじっくり育てていきます。
-
夜は冷えすぎないように
-
昼は蒸れすぎないように換気をして
-
水やりのタイミングや量を調整
この時期は、毎日苗の様子が気になって、
ついつい何度もハウスを覗きにいってしまいます👀
しっかりとした苗が育てば、田植えはもう半分成功したようなもの。
それくらい、苗づくりは米づくりの土台なんです🌱
3. 田植えは“チーム戦”!みんなで迎える大仕事🚜💨
田んぼに水を張り、代かきを終えたら、いよいよ田植えです。
今は田植え機がありますが、それでも田植えの数日はとても忙しく、**まさに“農家総出のイベント”**になります。
-
苗を軽トラックに積んで田んぼへ運ぶ人
-
田植え機に苗を補給する人
-
田植え機を操作する人
-
予備の苗やガソリン・肥料などを準備する人
家族や親戚、ご近所さんに手伝ってもらうことも多く、
田植えが終わるころには、
「おつかれさま!」とみんなで笑い合うのが恒例です😄
田植え機が走ったあと、
真っ白な水面に整然と並ぶ小さな緑の列。
あの景色を見ると、
「今年もいよいよ始まったな」と、身が引き締まる思いがします✨
4. 夏は“水・草・病気”との戦い💧🌿🦠
田植えが終われば一安心…
と言いたいところですが、ここからが本当の勝負です。
💧 水管理
-
深水にする時期
-
浅くする時期
-
中干し(いったん水を抜いて土を固める)
田んぼの状態や天候を見ながら、日々水位を調整していきます。
「今年は雨が多いから、排水を気を付けないと」
「暑さが続くから、水を切らさないように」
こうした判断を繰り返しながら、
稲が一番力を発揮できるようにサポートしていきます🌞
🌿 雑草との戦い
田んぼの中だけでなく、
あぜや水路にも草が生えてきます。
-
放っておくと、水の流れを塞いでしまう
-
虫や病気の温床になる
などの問題があるため、
草刈り機を背負ってあぜ道を何往復もします。
真夏の草刈りはとにかく暑いですが、
きれいに刈り終えたあぜ道を見ると、どこか誇らしい気持ちになります😊
🦠 病害虫のチェック
-
葉が黄色くないか
-
斑点や病斑が出ていないか
-
穂が出るタイミングでのいもち病やカメムシの被害
など、日々稲の様子を観察します。
異変があれば早めに対処し、稲穂に実がしっかり入るように守っていきます。
5. 秋、黄金色の田んぼで迎える“収穫のとき”🍂🍚
夏を乗り越えて、
田んぼ全体が黄金色に染まり始めると、いよいよ収穫の時期。
-
穂がしっかり垂れているか
-
籾の色・水分量はどうか
-
台風の予報はないか
などを見ながら、コンバインで刈り取るタイミングを決めます。
収穫の日、田んぼに立つと、
風が吹くたびに穂がサラサラと音を立てて揺れます。
その景色は何度見ても感動的で、
「今年もここまで来られたな」と、胸がいっぱいになります🌾
コンバインで刈り取った籾は、乾燥機で水分を調整し、
もみすり・精米を経て、ようやく皆さんのもとへ届けられる“白いお米”になります。
6. 田んぼは「お米工場」であり「自然のダム」でもある🌿💧🦆
米農家として感じているのは、
田んぼはお米を作るだけの場所ではないということです。
-
雨が降ったとき、一時的に水をためてくれる「小さなダム」
-
カエルやトンボ、野鳥など、たくさんの生き物のすみか
-
夏には地面の温度を下げ、涼しい風を運んでくれる“天然のクーラー”
田んぼがあることで、
地域の景色が守られ、生き物の多様性が保たれ、
水害の緩和にも一役買っています🦆
「田舎の風景」といってしまえばそれまでですが、
その裏側には、
毎年田んぼを守り続けている農家の手間と想いが詰まっているんです。
7. お米を“選ぶ”ことは、田んぼと地域を応援すること📣
スーパーに並ぶお米を手に取るとき、
「産地」や「生産者の名前」を見てくださる方が増えてきました😊
-
地元産のお米
-
顔写真やメッセージの入った生産者表示
-
農薬や肥料の使い方を工夫したお米
そういったお米を選んでいただけることは、
私たち農家にとって本当に大きな励みになります✨
お米を選ぶことは、
-
その田んぼを来年も維持すること
-
その地域の水・生き物・景色を守ること
にもつながっていきます。
「いつも同じ銘柄のお米だけど、たまには違う産地も試してみようかな?」
「地元のお米を買ってみようかな?」
そんな小さな一歩が、
農家と田んぼにとっては大きな一歩になるんです🚶♀️🚶♂️
8. 麦と米、二つの“いのち”を育てる農家として🌾🍚
私たちは、
-
秋から初夏にかけて麦を育て
-
春から秋にかけて米を育てる
というサイクルの中で一年を過ごしています。
忙しい日々の中でも、
-
初めて芽が出たときのうれしさ🌱
-
青く広がる田んぼを眺める気持ちよさ🌿
-
夕焼けに染まる麦畑・稲穂の美しさ🌇
そうした瞬間があるからこそ、
「また来年も頑張ろう」と思えるのだと思います。
9. 最後に…今日の一膳に“ありがとう”を🙏
今日、みなさんが食べたお茶碗一杯のごはん🍚
その一粒一粒には、
-
冬からの準備
-
春の苗づくり
-
夏の水管理や草刈り
-
秋の収穫
たくさんの季節と、たくさんの人の手間が込められています。
「いただきます」や「ごちそうさま」という言葉は、
食べ物そのものだけでなく、
そこに関わったすべての命や人に向けた言葉でもあると、
農家としてあらためて感じています😊
これからも、
安心して毎日食べられる“おいしいお米”と“国産の麦”を届けられるように、
一つひとつの作業と向き合いながら、畑と田んぼに立ち続けていきたいと思います🌈
もしどこかで、
麦やお米を見かけたら、
「ブログを書いていたあの農家かな?」と、
ちょっとだけ思い出してもらえたら嬉しいです😉✨
![]()
小浜あぐりの米米日記~パンも麺もここから生まれる!🌾~
皆さんこんにちは!
小浜あぐり合同会社、更新担当の中西です。
~パンも麺もここから生まれる!🌾~
今日はその中でも、麦農家としての一年の仕事や、国産小麦に込めている想いをお話ししてみたいと思います。
スーパーの棚には当たり前のように並んでいるパンや麺、焼き菓子たち。
実はその一枚一枚、一口一口の“元”になっているのが、私たちが育てている麦なんです🌾🥐
「小麦って、いつ種をまいて、どんなふうに育てているの?」
「国産小麦って、輸入小麦と何が違うの?」
そんな疑問をお持ちの方に、現場目線で分かりやすくお届けしていきます✨
1. 麦農家の一年は“秋”からはじまる🍂
麦と聞くと、なんとなく「初夏の黄金色の景色」をイメージする方が多いかもしれません。
でも実は、私たち麦農家の一年は“秋”から本格的にスタートします。
秋のはじめ、稲刈りがひと段落する頃から、
麦をまく畑の準備が始まります🚜
-
稲を刈り取った後の田んぼを乾かす
-
トラクターで耕して、残った稲わらをすき込む
-
必要に応じて石灰や堆肥をまいて、土の状態を整える
ここまでやって、ようやく麦の“ベッドづくり”が完了です。
この土づくりの段階で手を抜くと、
春になってから麦がうまく育たなかったり、病気が出やすくなったりするので、実はとても大事な工程なんですよ😊
2. 小さな種から“麦秋”へ…麦の成長ストーリー📖🌾
畑の状態が整ったら、いよいよ播種(はしゅ:種まき)です。
麦の小さな種を、専用の機械で等間隔にまいていきます。
播種後、しばらくすると、
ひょこっとかわいい芽が顔を出します🌱
この時期の麦畑は、うっすらと緑色のじゅうたんのようで、とてもきれいです。
そこから冬にかけて、麦はゆっくりと成長します。
寒さの中でじっと耐えながら、根をしっかりと張り巡らせ、
春に一気に伸びるための“準備運動”をしているようなイメージです💪
やがて春になると、
-
茎がぐんぐん伸び
-
穂が顔を出し
-
緑色から少しずつ黄金色へ
田んぼの緑が深まる頃には、麦畑はまるで金色の波のように揺れ始めます。
この初夏の季節を、私たちは**「麦秋(ばくしゅう)」**と呼んでいます。
“秋”という漢字がついていますが、実際は初夏。
麦にとっての「実りの秋」が、この時期に訪れるというわけですね😊
3. 麦作りの大敵は“天気”と“病気”と“雑草”🌧🦠🌱
麦づくりで難しいのは、天気に左右されることがとても多いところです。
-
播種のタイミングで大雨が続く
-
冬場に雪が多すぎて苗が傷む
-
春の長雨で病気が出やすくなる
-
収穫前に大雨や強風が来る
こうしたことが重なると、
せっかく育ててきた麦が倒れてしまったり、
品質が落ちてしまうこともあります💦
また、麦は**病気(さび病・うどんこ病など)**や
雑草との競争にも弱い一面があります。
-
病気がひどいと、穂が十分に実らず収量ダウン
-
雑草が生い茂ると、養分や光を奪われてしまう
そのため、
-
播種の深さや間隔を調整して、強い苗を育てる
-
土の状態を良くして、病気の出にくい環境を整える
-
雑草が大きくなる前に対策を打つ
など、日々の小さな工夫の積み重ねがとても大事になってきます🌱
4. 国産小麦の魅力って何?🇯🇵✨
「小麦はほとんど輸入なんでしょう?」
そう思っている方も多いと思います。
たしかに、日本の小麦自給率はまだ高くはありません。
でもその中で、
**“あえて国産小麦を選んでくださるパン屋さん・製麺所・お菓子屋さん・ご家庭”**が増えています😊
国産小麦には、こんな魅力があります👇
-
産地や生産者の顔が見える安心感👨🌾
-
品種ごとの個性(香り・甘み・モチモチ感)が分かりやすい
-
輸送距離が短く、フレッシュな状態で届きやすい
-
地元で育てた小麦を、地元のパン屋さんやうどん屋さんが使ってくれる“地産地消”
パンに向いた品種、麺に向いた品種、お菓子に向いた品種など、
最近は日本各地で個性的な小麦の品種も増えてきています。
私たちの地域でも、
-
パン屋さん向けの小麦
-
うどん・ラーメン用の小麦
といった形で、用途を意識した栽培に取り組んでいます🍞🍜
5. 麦農家だから見える「一粒のありがたみ」🌾🙏
収穫が近づいた麦畑に立つと、
風に揺れる穂の“ザワザワ…”という音が聞こえてきます。
ひとつの穂にはびっしりと実がつき、その一粒一粒が半年以上かけて育ってきた“命”のように思えてくるんです。
-
秋に種をまいた日
-
冬の寒さを耐えた景色
-
春の強風に耐えながら伸びていく姿
-
病気が心配で、葉をじっと見て回った日
そうした日々を思い出しながら、
コンバインで麦を刈り取る瞬間は、何度経験しても胸が熱くなります。
収穫した麦は乾燥・調整を経て、製粉会社さんへ。
そこからパン屋さん、うどん屋さん、お菓子屋さん、そして皆さんの食卓へとバトンが渡っていきます🍽️
私たちは普段、
お店に並んだパンやパスタを見るたびに、
「この一部には、うちの麦も入っているかな?」と想像してしまいます😌
6. 麦と米、二つの作物をつなぐ“二毛作”という知恵🔁
私たちの地域では、
**「米→麦→また米」**というように、
一年の中で田んぼをフル活用する“二毛作”を行うことも多いです。
-
秋に稲刈りをする
-
そのあとすぐに麦をまく
-
初夏に麦を刈り取る
-
その後ふたたび田植えをする
こうすることで、
-
土地を有効に活用できる
-
作物の種類を増やして、収入の柱を分散できる
-
麦と稲、それぞれの根やわらが土を豊かにしてくれる
といったメリットがあります🌱
ただし、
作業の切り替えが早く、体力的にはハードな一年でもあります💦
それでも、麦と米、両方の収穫を迎えたときの達成感は格別です✨
7. 麦農家としてお客さまに伝えたいこと💬
最後に、麦農家としてお伝えしたいことをいくつかまとめてみます👇
-
パンや麺、お菓子を食べるとき、「どんな小麦でできているんだろう?」と少しだけ想像してみてほしい😊
-
国産小麦を使っているお店を見かけたら、それは農家にとっても大きな励みです💪
-
麦畑の黄金色の景色を見かけたら、「今、ちょうど麦の収穫時期なんだな」と思い出してもらえたら嬉しいです🌾
私たちは、
“毎日の何気ない一口”を支えるために、季節ごとに違う景色の中で黙々と麦を育てています。
これからも、
安心しておいしく食べてもらえる麦づくりを続けていきますので、
もしどこかで「国産小麦使用」の文字を見かけたら、
その裏側にいる農家のことも、ほんの少しだけ思い浮かべてもらえたら嬉しいです🌈
![]()

